コラム
コラム

自宅での療養生活を送るなかで、「マッサージを受けさせてあげたいけれど、通院が難しい」「継続的にケアを続けたい」と感じることはありませんか? そんなときに役立つのが、自宅まで専門職が来てくれる“訪問マッサージ”です。
「保険が使えるって聞いたけど、条件は?」「費用はどのくらいかかるの?」といった疑問を持つ方も多いかもしれません。この記事では、訪問マッサージに医療保険を利用するための条件や、対象となる症状、費用の目安までをわかりやすくまとめています。
ご家族のケアに悩む方や、介護を支える立場の方にとって、少しでも安心材料となれば幸いです。
ご家族の体調や通院の負担が気になっている方へ
自宅で受けられる訪問マッサージについて詳しく知りたい場合は、お気軽に皆んなの訪問リハビリマッサージまでご相談ください。
▶︎ ご家族の方のお問い合わせはこちら
▶︎ ケアマネージャー・施設管理者様のお問い合わせはこちら

訪問マッサージ(在宅マッサージ)は、高齢や病気、身体的な理由で外出が難しい方が、自宅で専門家によるマッサージを受けられるサービスです。この記事では、訪問マッサージについて、その定義、サービス内容、メリットについてわかりやすくお伝えします。
訪問マッサージでは、主に以下のようなサービスが提供されます。
これらのサービスは、利用者の状態やニーズに合わせて、専門家によって提供されます。
訪問マッサージには、以下のような多くのメリットがあります。
これらのメリットから、訪問マッサージは、自宅療養をされている方々にとって、非常に有効な選択肢と言えるでしょう。

訪問マッサージの医療保険適用は、特定の疾患が対象となります。基本的には、筋麻痺や関節拘縮、脳血管疾患の後遺症、そのほか医療上マッサージが必要とされる状態の方が該当します。
たとえば、脳梗塞や脳出血の後遺症で麻痺や関節の動きが悪くなった方、パーキンソン病や脊髄損傷などで寝たきりになっている方などが対象です。こういった疾患により、自力での移動が難しく、医師がマッサージを必要と認めた場合、医療保険が適用されることがあります。
医療保険を使って訪問マッサージを受けるには、医師の同意書が欠かせません。これは、医師が患者さんの状態を確認し、訪問マッサージが必要だと判断したことを証明する書類です。
同意書には、患者さんの病名や状態、マッサージの必要性、施術の頻度などが記載されます。訪問マッサージを受ける前に、かかりつけ医に相談し、同意書の発行をお願いする必要があります。発行には診察料がかかることもあるため、事前に確認しておくと安心です。
また、施術者はこの同意書をもとに内容を確認し、それに沿った施術を行っていきます。
皆んなの訪問リハビリマッサージでは、医師と提携しているため、訪問マッサージサービスの開始の際、同意書の取得を代行して行っています。
手続きに不安のあるご家族の方も、安心してご利用いただけます。
訪問マッサージの費用は、施術の内容や時間、利用者の身体状態などによって異なります。一般的には、施術料に加えて、出張費やその他のサービス料が含まれることがあります。
医療保険が適用される場合の自己負担額は、年齢や所得により変わりますが、通常は1割から3割程度です。実際の金額については、訪問マッサージを提供している事業者に直接確認しておくと安心です。
訪問マッサージにかかった費用は、条件を満たせば医療費控除の対象になります。医療費控除とは、1年間に支払った医療費の合計が一定額を超えた場合に、所得税の還付や住民税の軽減が受けられる制度です。
この控除を受けるためには、確定申告が必要です。領収書は大切に保管し、必要な情報を記載した申告書を税務署に提出することになります。控除の金額は収入や支払った医療費の合計額によって異なりますが、制度を活用することで税金の負担が軽くなる可能性があります。
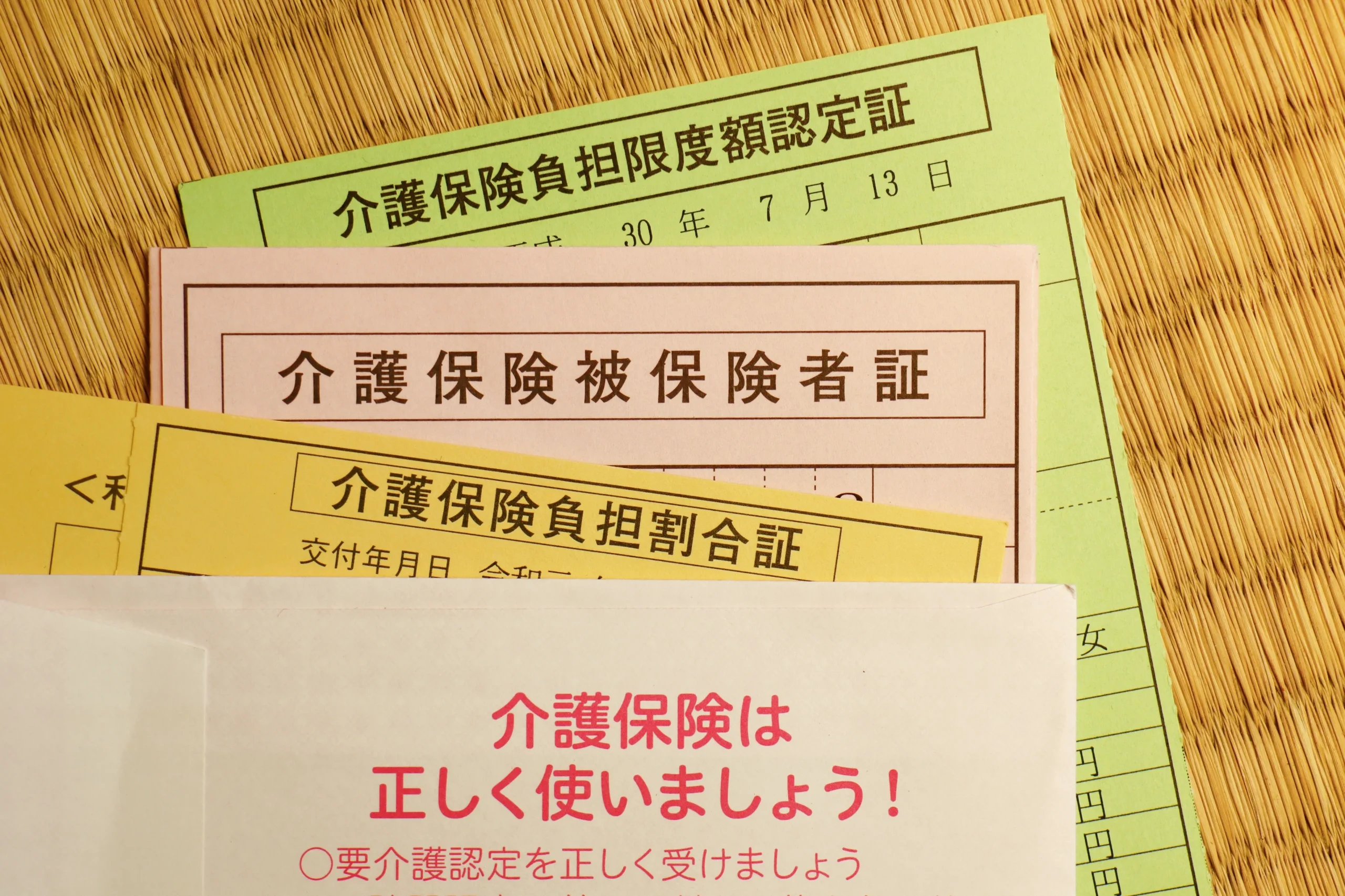
介護保険と訪問マッサージは、それぞれ異なる制度ですが、高齢者の健康と暮らしを支えるための重要な手段です。必要に応じて連携しながら活用することで、より良いケアが期待できます。
訪問マッサージは、介護保険ではなく医療保険が適用されるサービスです。そのため、同一の内容で介護保険サービスと訪問マッサージは、原則併用することはできません。ここでは、両制度の違いと利用時の注意点について整理します。
介護保険は、要介護・要支援認定を受けた高齢者が、自立した生活を続けられるよう支援するための制度です。訪問介護、通所介護(デイサービス)、短期入所生活介護(ショートステイ)など、生活支援や介助を目的としたサービスが提供されます。これらは市区町村に申請し、ケアマネジャーと一緒にケアプランを作成して利用します。
訪問マッサージは医療保険の対象です。対象となるのは、医師の同意書があり、筋麻痺や関節拘縮などの症状を持つ方で、外出が難しく自宅での施術が必要な方です。医師が「医療上マッサージが必要」と判断した場合に限り、保険適用が認められます。
一方で、介護保険は、要介護や要支援の認定を受けた方が、日常生活を送るうえで必要な支援を受けるための制度です。訪問介護やデイサービス、ショートステイなど、生活面のサポートを中心としたサービスが提供されます。
つまり、訪問マッサージは医療的な必要性に基づくサービスであり、身体機能の維持・改善を目的とした施術が中心です。それに対し、介護保険サービスは生活の質を保つための支援が主な目的となっています。どちらの制度も高齢者や身体に不自由のある方の生活を支えるものですが、仕組みも目的も異なるため、同じ内容を重複して受けることは原則できません。
訪問マッサージを利用する際には、以下の点に注意が必要です。
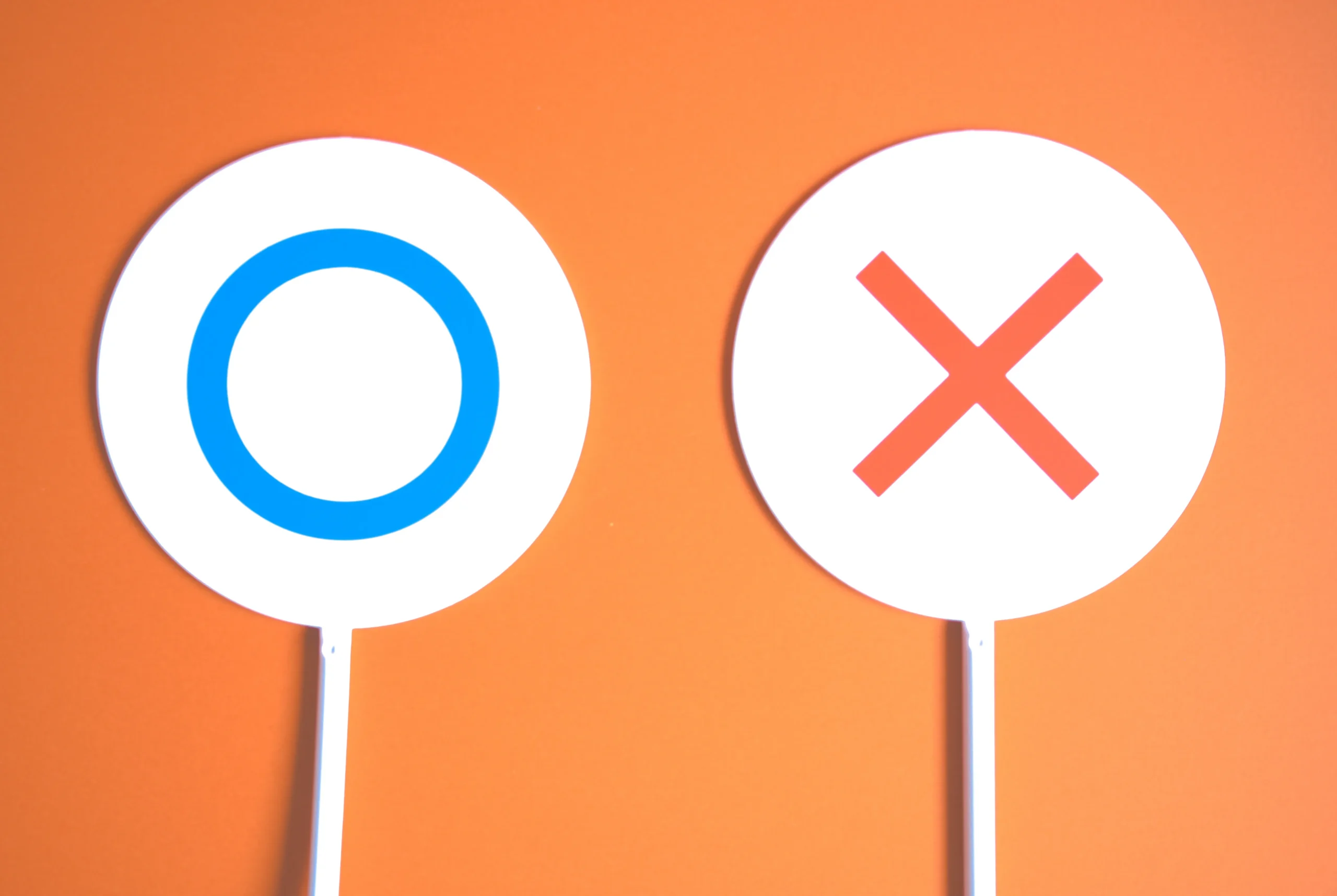
訪問マッサージを安心して受けるためには、信頼できる事業者を選ぶことが大切です。以下の点をチェックしましょう。
信頼性の高い事業者を見つけるには、以下の方法がおすすめです。
訪問マッサージの利用を開始するまでの流れは、以下の通りです。
訪問マッサージを利用する際には、いくつかの書類が必要となります。
訪問マッサージを受けるにあたって、いくつかの点に気をつけておくと安心です。まず、施術を受ける方の症状や状態によっては、医療保険が使えないケースもあります。たとえば、病状がすでに安定していて医師がマッサージを必要と認めていない場合には、費用が全額自己負担になることがあります。
また、施術を担当する方の技術や経験にも差があります。施術を依頼する前に、事業者のホームページや紹介資料などを通して、どんな施術者が在籍しているのか確認しておくと安心につながります。
施術を安全に受けるためには、体調や持病、アレルギーなどの情報を正確に伝えておくことも大切です。こうした情報があれば、施術者が無理のない方法を選び、身体への負担が少ない形で対応しやすくなります。
訪問マッサージに関して、利用を検討している方から寄せられる質問の中から、よくあるものをいくつか紹介します。
Q. どんな人が訪問マッサージを受けられるの?
A.歩行が困難な方や、寝たきりの状態で通院が難しい方が対象です。医師による同意が必要となるため、かかりつけ医への相談が出発点になります。
Q. 料金はどれくらい?
A.医療保険が使える場合、自己負担は1〜3割の範囲に収まることがほとんどです。ただし、保険が使えない場合は全額自己負担となるため、事前の確認が大切です。料金の詳細は、利用を検討している事業者へ直接問い合わせると安心です。
Q. どんな服装が適しているの?
A.施術を受ける際は、締め付けがなく、リラックスできる服装が好ましいです。動きやすい部屋着などを選ばれる方も多くいらっしゃいます。必要であれば、着替えの補助も行っています。

ここまで、訪問マッサージの概要や医療保険の適用条件、費用の仕組み、介護保険との関係、事業者選び、利用までの流れ、注意点などについて紹介してきました。
医療保険の仕組みはやや複雑に感じるかもしれませんが、信頼できる医師や事業者と相談を重ねていくことで、不安を取り除きながら進めていくことができます。
ご自身やご家族の体調にあわせて、訪問マッサージという選択肢が生活を少しでも快適にする助けになれば幸いです。
訪問マッサージを安心して利用するために、正しい情報を知ることが第一歩です。
ご不明点や導入に関するご相談は、皆んなの訪問リハビリマッサージまでお気軽にお問い合わせください。
▶︎ ご家族の方のお問い合わせはこちら
▶︎ ケアマネージャー・施設管理者様のお問い合わせはこちら
